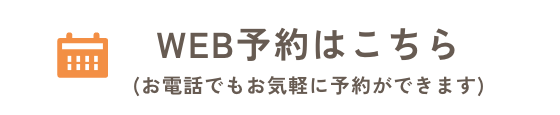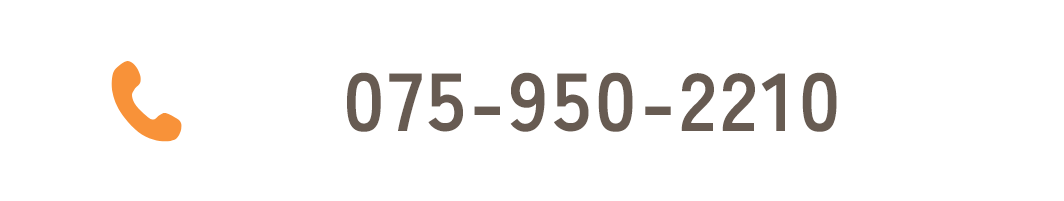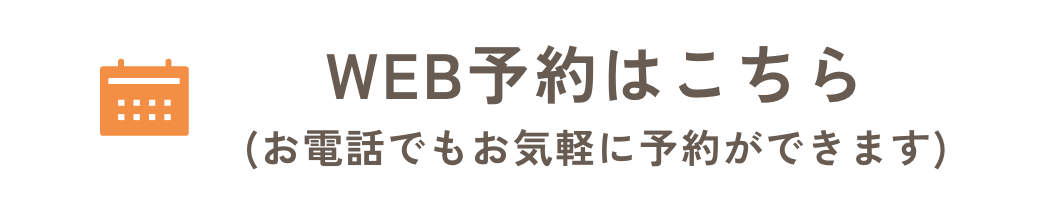お気軽にお問い合わせください
- 診療時間
- 9:00~13:00 / 16:00〜19:00
- 休診日
- 木曜午後 / 日曜 / 祝日

骨の密度が低下して骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。
日本には1000万人以上の患者さまがいるといわれ、年齢が上がるにつれて増加傾向にあります。
健康な骨と比べると、骨粗しょう症の骨の中身がスカスカの状態になっているため、軽い転倒や運動などでも折れやすくなり、日常生活の動作やくしゃみだけで骨折してしまう場合もあります。
自覚症状がないまま進行してしまい、背骨(脊椎)の変形や身長が縮んだことで気づくこともあります。
骨粗しょう症によって、大腿骨頚部骨折や頚椎圧迫骨折などになってしまうと、長期間にわたってベッド生活を送ることになります。身体の機能が低下し、寝たきりになってしまうケースもあり、早期発見と早期治療が肝心です。
骨粗しょう症は閉経後の女性に多く、ホルモンバランスの変化や老化に起因していると考えられます。
閉経後の女性は卵巣からのエストロゲンという女性ホルモンが減少します。このホルモンは骨の形成を促す役目があるため、分泌量が減ったことで骨が弱くなってしまうのです。
主にエストロゲンの欠乏や加齢によって起こるもので、骨粗しょう症のほとんどを占めています。栄養の偏りや無理なダイエットなどもリスクになります。
閉経や加齢以外の何らかの原因によって、二次的に起こるものです。糖尿病をはじめとする生活習慣病、関節リウマチ、先天性疾患、薬物などの影響によって引き起こされます。

骨粗しょう症の検査機を使って患者さまの骨の状態を測定いたします。採血の検査も見て診断し、内服薬や注射薬などを用いた治療を行います。 薬物療法だけでなく、食事療法、運動療法を組み合わせて改善し、患者さまの健康な生活をサポートしていきます。 高齢の患者さまは、本人の自覚がないまま骨粗しょう症が進行しているケースが多く、年々患者さまの数も増えています。ちょっとした転倒などで骨折につながるリスクがあるため、早期発見早期治療ができるよう、定期的な検診をおすすめしています。
骨粗しょう症の薬には、大きく分けて3種類の薬があります。
1. 骨の減少を抑える薬(カルシトニン、ビスホスホネート、SERM、デノスマブなど)
2. 骨の形成を助ける薬(副甲状腺ホルモン薬、ビタミンK2など)
3. カルシウム吸収を促進する薬(カルシウム薬、活性型ビタミンD3製剤など)
これらの薬剤から、患者さまの状態に合わせて適切なものを選択し、内服薬または注射薬として使用します。
骨粗しょう症の改善と予防には、食事から栄養素を摂取することが大事です。特にカルシウムを多く含んだ食材を取り入れ、栄養バランスのよい食事を心がけていただきます。
摂取したい栄養素
・カルシウム(牛乳などの乳製品、小魚、大豆、海藻、緑黄色野菜など)
・ビタミンD(魚類、きのこ類など)
・ビタミンK(納豆、ブロッコリーなど)
・タンパク質(肉、魚、豆、卵など)
過剰摂取に注意する栄養素
・リン(加工食品、清涼飲料水など)
・ナトリウム(食塩、しょうゆ、加工食品など)
・カフェイン(コーヒー、紅茶など)
・アルコール(酒類)
運動によって骨に適度な負荷をかけ、骨量を増やしていきます。筋力をつけて体のバランスを高め、転倒を予防する効果もあります。
当院のリハビリルームで筋力トレーニングをしたり、日常生活の中でウォーキングをしたり、患者さまが無理なくできる方法で運動を取り入れていきます。
現在の健康状態、気になっている症状やなどについて確認をします。
骨量の測定・・・DXA法というX線を使った装置で体の部位をスキャンし、骨の密度を測定します。
レントゲン・・・胸椎や腰椎を撮影し、骨の状態を判定します。
骨代謝マーカー・・・骨の代謝の状態を、血液検査によって測定します。
検査の結果をもとに患者さまの状態を把握し、どんな治療が適切か診断をします。
薬物療法、食事療法、運動療法を組み合わせ、骨粗しょう症を治療していきます。